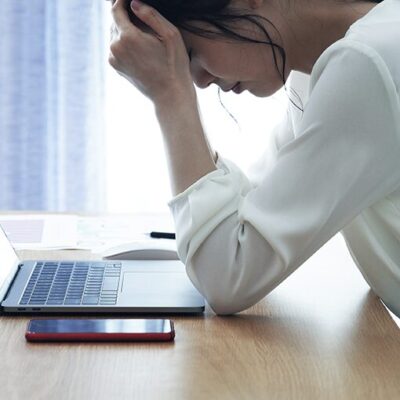前回認知症予防の日が昨年に制定されたお話をしました。今後数回にわたり、認知症予防についてお話していきたいのですが、まず、前提としてここで私がお話しするのは認知症の中でも「アルツハイマー型認知症」「脳血管型認知症」「レビー小体型認知症」「前頭側頭葉型認知症」「アルコール性認知症」この5つの疾患について述べたいと思います。認知症全てにあてはまるわけではない、例えばクロイツフェルト・ヤコブ病など特定の頻度の低い疾患は個別に対処法がありますし、逆にアルツハイマー型認知症だけのことを述べているわけでもないことをご理解ください。もちろんこの短い文章ですべてを説明するのは無理なのですが、 最低限知っておいてほしいキーワードを並べています。参考にしていただければと思います。 この5つの疾患について説明いたします。
1、 アルツハイマー型認知症
脳にアミロイドβやタウと呼ばれる特殊なたんぱく質が溜まって神経細胞に影響を与え、認知機能に障害が起こると考えられている。 日本人の認知症の約半数かそれ以上といわれている。
危険因子 加齢(65歳以上で8人に1人、85歳以上で2人に1人)、女性、生活習慣病、甲状腺機能異常、頭部外傷の既往
2、 脳血管型認知症
脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血などの病気により脳の細胞に酸素や栄養がいかなくなることで障害が起きる。日本人では微小な脳梗塞、ラクナ梗塞が原因でおこる皮質下型脳血管型認知症が多いといわれている。
危険因子 加齢、男性、生活習慣病、喫煙、肥満
3、 レビー小体型認知症
大脳の皮質の神経細胞内に「レビー小体」と呼ばれるたんぱく質が溜まることによっておこる。1976年に小阪憲司医師(横浜市立大学名誉教授)によって発見されました。大きな特徴は、幻覚(幻視)がハッキリ現れる(約80%)、また体の硬直がはじまり動作全般が遅くなる、転倒のリスクが高い、パーキンソン病に似ている症状がみられます。
危険因子はまだわかっていませんが、初期に 嗅覚障害やレム睡眠行動障害(大きな寝言など)がみられるといわれています。
4、 前頭側頭葉型認知症(FTD)
脳の前頭葉と側頭葉が萎縮して血流低下することによって、脳の機能に障害が起こる。タウ蛋白やTDP-43という蛋白が関与がわかってきているが、まだ、解明されていないことが多い。 認知症の10人に1人、65歳以下に発症することが多い。 男女差はほとんどなく、家庭内で遺伝する傾向。 脳の中で、前頭葉は「人格、社会性、言語」を、側頭葉は「記憶、聴覚、言語」を主につかさどっています。 そのため、FTDを発症すると特徴的な症状が出ます。
A,社会性の欠如 万引きのような軽犯罪、身だしなみに無頓着
B,抑制が効かない 相手に対し暴力をふるうこともあります
C,常同行為 同じ道順、同じ動作をとりつづける
D,感情鈍麻 他人に共感できない、感情移入できない
E,自発性な言葉の低下 相手に言われたことをオウム返し
5、 アルコール性認知症
アルコールを多量に飲み続けたことで、脳血管障害やビタミンB1欠乏による栄養障害などから脳の機能に障害が起こる。
危険因子 アルコール多飲、栄養不足
アルコール適量の目安(厚生労働省 健康21) ビール(アルコール度数5度 中瓶 1本 500ml) 日本酒(アルコール度数 15度 1合 180ml) ウィスキー(アルコール度数43度 ダブル1杯 60ml) ワイン(アルコール度数 14度 グラス2杯 180ml) 缶チューハイ(アルコール度数 5度 1.5缶 520ml)
以上が日本でよくみられる認知症です。アルツハイマー型認知症は最近よく耳にしますが、それ以外の疾患はまだあまりなじみがなく、別の認知症と鑑別が難しいものもあり、一様に扱われることが多いのが現状と思います。次回には、認知症予防について「詳しくかつ、わかりやすく」をモットーにお話しできたらと思います。 今回も御一読頂き誠にありがとうございます。
参考:現代臨床精神医学 金原出版株式会社 大熊輝雄
参考:厚生労働省 健康日本21 日本認知症予防学会 ホームページ