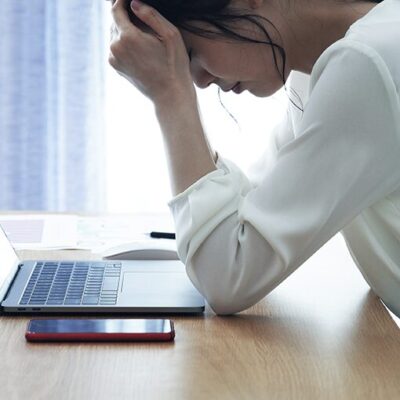人間はいつの頃から笑うこと、愉しむことを無くしてしまった。それとは対局に、怒り(殴る蹴る、大声で暴言を吐く等)が増加し、また悲しみ(哀しみ)も人々の会話から消え去ろうとしている。戦後70年近くなり、戦前戦中を生きぬいた人々も少なくなり、毎年行う終戦記念日の催しに参加される人々も減少しているだろう。これも一つ変化であり、平成の現在、この社会から特に「笑う」ことの場が無くなっている。
なぜだろうか。例えば、今日のテレビはデジタル型であり、アナログ型ではテレビを見れない社会に変化している。デジタルとアナログの違いは、光の二重性にある。この現象を証明した人物はアインシュタインである(1906年)。光のこの二重性が、科学技術の進歩の結果、アナログ時代よりさらにアナログの言語に有る曖昧さが無くなり、今や言葉は情報の伝達化に変化している。この事は、人の脳の情報ネットワークでデジタル型が主流となる過程に於いて、脳のネットワーク情報(会話を含めて)は、言葉とか文(ふみ)の持つ言葉を交わす折の響きあるいは音韻かつ文章の書体の味などが失われつつある。科学技術の変化が脳のネットワークにも変化を生じているかもしれない。いわゆる人が一つの素子となり、社会が脳に変わって人間を操作しているのだろう。この現象も地球上の進化であるだろうか。
「笑いと余韻」が消えていく過程が、個々の身体、とりわけ脳を病んでいる患者を診察する折、以上のことを常々感じさせられる日々である。
初夏自宅にて 2012年6月3日
今川正樹