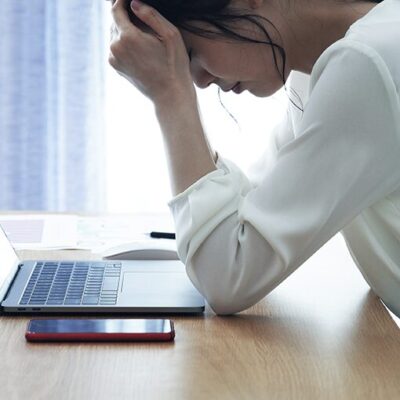今回も、認知症専門医がおススメする、デール・ブレデセン氏の著書、『アルツハイマー病 真実と終焉』(ソシム、監修者:白澤卓二氏・訳者:山口茜氏)。その中から一部を抜粋してご紹介いたします。
何度か当ブログでもエッセンスをお伝えしていましたが、この機会に、一度拝読頂ければ幸甚です。少しでも見やすく、理解しやすいように時折箸休め的な挿絵を入れております。原著にはない挿絵なのでご注意ください。
アルツハイマー病は「脳の防御反応」!?
また、アルツハイマー病の主要な定説に、異論を唱える発見もある。この深刻な病が、正常で健康な脳のプロセスがおかしくなった結果であることを示すのは、脳はなんらかの損傷、感染、その他の攻撃(色々な種類を説明しよう)を受け、身を守るよう反応する、という発見によって明らかになった。
この防御メカニズムには、アルツハイマー病関連のアミロイド産生も含まれる。そう、読み違えたわけではない。何十年も悪く言われ続け、誰もが除去しようとしてきた、まさにそのアミロイド自体が、脳の防御反応の一部だったのだ。それ故に、アミロイドを除去しようとしても、アルツハイマー病患者にはあまり有用でなかったのも不思議ではない。
したがって、現在の定説とは逆で、アルツハイマー病であるといわれるものは、実際のところ防御反応であり、防御の対象を具体的に言うと、3つの異なるプロセスー炎症、栄養素とシナプスを支えるその他分子の欠乏、毒物への曝露―である。
毒物の代表例として、水銀が挙げられている。
これについては、本書の第6章でより詳細に述べるが、今のところは、このシンプルなメッセージを強調させていただきたい。アルツハイマー病に、3つの異なるサブタイプが存在する(そしてしばしば、これらサブタイプが組み合わさっている)という認識は、アルツハイマー病の評価法、予防法そして治療法に深遠な意味を持つのだと。
この発見はまた、認知機能の喪失や、軽度認知機能障害、主観的認知機能障害の捉えがたい状態を、本格的なアルツハイマー病に進行する前に、もっとうまく治療できることも意味する。
本書の第7章では、認知機能低下の理由や、そのリスクとなるものを特定する検査を学ぶ(自分でアルツハイマー病になるようなことをすでに行っているかもしれない)。
検査は必要だ。というのも、認知機能を低下させる要因は往々にして多岐にわたり、他の人の要因とは異なる可能性が非常に高いからだ。だからこそ、これらの検査で各人に個別化したリスクプロファイルが手に入り、治療を最適化するにはどの要因に対処すればよいかがわかる。
それぞれの検査の背景にある論理的根拠も教えよう。つまり、その検査で評価した生理的パラメータ[身体の生理状況により変化する数値]が脳機能とアルツハイマー病にどうかかわるのか? ということだ。本書の第7章ではこの〝認知機能検査〞に含まれる検査をまとめ、背景にある基本理念を解説する。
本書の第8章と第9章は、検査結果に応じて行うべきことの解説になる。認知機能の低下を回復し、将来のリスクを下げるために対処しなければならない基本事項―炎症/感染、インスリン抵抗性、ホルモンと必要栄養素の枯渇、毒物曝露、喪失した、あるいは機能不全になった脳の結合(シナプス)の交換と保護―を考察する。これは「万人に効く」アプローチではない。リコード法は、検査結果に基づき、1人1人にオーダーメード化される。
つまり、その人固有の生理機能に最適化するため、リコード法のバージョンは、すべて他の人とは異なる。もちろん、リコード法に効果があるということ、認知機能の低下を予防し回復させるというまさにこの事実こそが、独創的かつ斬新だ。しかし、それは個別化に焦点を合わせて初めて実現する。
今後の医療は、東洋医学の核心に近づく可能性も
本書の第10章〜第12章では、最高の治療結果を出して維持する秘訣を解説する。ここでは、うまくいかなかった場合に行う別の方法を提示し、認知機能の回復を成功させるだけでなく、このアプローチに向けられてきた疑問や批判に対応する。
19世紀現代医学の到来により、医師は、例えば、高血圧やうっ血性心不全、関節炎といった具合に病気を診断し、高血圧には降圧薬というように、万人に効く治療薬を処方するよう訓練されてきた。これは今、ゆっくりと変化しており、がんの精密治療では腫瘍の遺伝子プロファイルにより処方薬が決められるようになっている。
個別化医療を強く求める動きの中で、私たちは伝統中国医学(TCM)やアーユルヴェーダ認知症を食い止める第1章医学のような東洋医学の核心に近づく可能性がある。
アーユルヴェーダの体質論
これら伝統治療を行う古代の医師たちは、特定の病気の分子生物学的な詳細は、何も知らなかったが、「高血圧」のような単一の病気に的を絞る代わりに、人間を丸ごとひとつの存在として治療する専門家だった。新しい医学―21世紀の医学は、近代西洋医学と東洋の伝統医療の粋を結集し、分子メカニズムの知識を、1人の人間全体の理解へとつなぐものである。
新しい医学により、問題が「何」であるのか単に問うことを超え、問題が「なぜ」あるのかを問うことが可能になった。なぜかと問うことは、アルツハイマー病の予防と治療でもわかるとおり、状況を一変させるのだ。
デール・ブレデセン『アルツハイマー病 真実と終焉』第一章を中心に抜粋した文章とイラストでお話しして参りました。この続きが気になる方は是非、ご一読ください。タメになることが多く載っております。
ここでとりあげられたリコード法、当院でもその考えの元、食事指導、サプリメント、など当院のエビデンスに基づいた治療を行っております。また、漢方や東洋医学に基づいた治療もさせて頂いております。
ご興味ある方は是非当クリニックにお電話ください。
今回も御一読いただき誠にありがとうございました。
文献1)デール・ブレデセン『アルツハイマー病 真実と終焉』(ソシム、監修者:白澤卓二氏・訳者:山口茜氏)
文献2)大熊 輝雄:現代臨床精神医学第12版 金原出版株式会社
文献3)幻冬舎 GOLD ONLINE 新刊書籍を試し読み